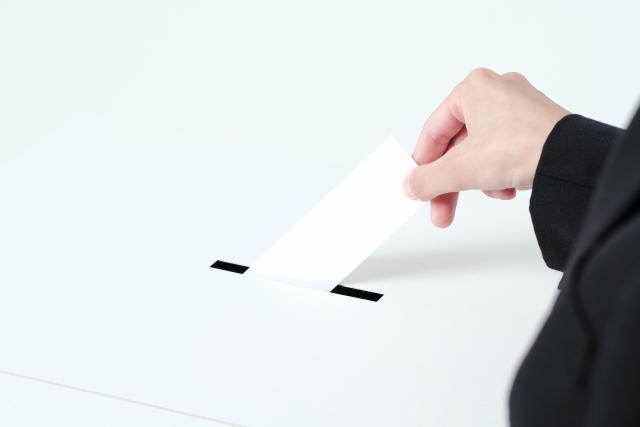現在開会中の臨時国会において、衆議院議員の定数削減の1割削減を目指す政策を実現する見通しとなっています。
高市総理大臣就任によって浮上してきた衆院議員定数の削減問題とは、どのような問題なのでしょうか?
衆院議員定数の削減問題の中身について、解説します。
なぜ衆院議員定数の削減が問われるのか
現在、日本の衆議院議員の定数は465人であり、うち289人は小選挙区選出議員、176人は比例代表選出議員です。
衆院議員定数の削減問題については以前から言われており、2012年には民主党の野田佳彦首相と自民党の安倍総裁との間で定数削減問題を含めて議論されていました。
定数削減を自民党の公約として解散総選挙が実施され、自公連立政権の安倍内閣が成立したのですが、当時は定数削減が果たされなかったのです。
今回、自民党が与党となったものの過半数に満たなかったことで各党が激しく争っていた10月中旬頃に、再び定数削減問題が浮上してきました。
公明党が与党から離脱して自民党だけでは次期政権が難しい情勢になった際、自民党に協力した日本維新の会が定数削減の成立を再優先するよう持ち掛けたのです。
維新の吉村洋文代表は、自民党に政策合意を迫った際に大阪の副首都構想、社会保障改革、衆院議員定数の1割削減の3つの条件を提示しました。
7月の参院選で自民党が敗北したのは、有権者の厳しい目線があったことが主な原因です。
自民党の中でも有力な議員が中心となって、政治資金を集めて裏金をプールしていた裏金問題は、まだまだ火種が残されています。
裏金議員と呼ばれる議員の復権問題などもあり、自民党の自浄能力には疑問符が付いたままだった中で、議員定数の削減の必要性が再考されるようになったのです。
自民と維新が10月20日に交わした合意書では、衆院議員定数を1割削減するための法案を提出し、成立を目指すことが明記されています。
また、国民民主党の玉木代表も関連法案の成立は同党が賛成すれば問題ないという見解を示しており、「協力するから冒頭で処理しよう」と発言しているのです。
ところが、自民と維新の政策協議において、当初は副首都構想と社会保障改革の2つだけが絶対条件だったことが、メディアでは報道されました。
定数削減については、突然両党の間で浮上したとされているため、論点を献金禁止からずらすために言い始めたのではないかといわれているのです。
政治献金問題を棚上げした形で一気に進み始めたため、定員削減については異論も少なくありません。
衆院議員定数の削減で起こる変化
もし、自民・維新が主張している衆院議員の1割削減が実現した場合は、どのような変化が起こるのでしょうか?
衆院の議員定数の削減は衆院定数の1割程度とされていますから、小選挙区か比例代表かを問わず、全体で40〜50人減らすことになります。
削減の具体案はまだ自民・維新側から示されていないのですが、維新の案では小選挙区には手を付けず、比例代表を50人程度減らすことになっているのです。
実際、維新の藤田文武共同代表は10月24日の記者会見において、「比例代表の削減が一番スピーディーだ」と強調しました。
比例代表が削減されると、小選挙区よりも比例代表での選出が多い政党やそもそも勢力の小さい政党にとってより大きな打撃となるでしょう。
読売新聞の試算によると、比例代表50議席削減が実現すると小選挙区も含めた議席の減少率は自民党で9%減、立憲民主党で6%減、維新で13%減となります。
しかし、比例代表での当選者が多い公明党と共産党はいずれも25%減、参政党と日本保守党はともに67%減という結果になるのです。
歴史をひも解くと、衆院の定数は常に一定というわけではなく、過去に何度も是正されてきたことが分かります。
戦後、新生・日本の衆院は468人でスタートしたのですが、人口の増加や高度経済成長に伴う大都市圏への人口流入などにより定員を増やしてきたのです。
米国から返還された沖縄県、および鹿児島県の奄美群島区も加わったことで、1986年には今よりも50人近く多くなりました。
高度経済成長が終わってバブル経済も崩壊すると、政界にも影響が及び改革などが必要となったのです。
さらに時間が経ち20世紀末に近づくと、選挙自体の制度にも変化が訪れて議員も減らされていきました。
衆議院議員選挙で選挙区が変化したことも、議員が減らされる傾向に一役買うこととなったのです。
竹下登内閣はリクルート事件などの影響を受けて崩壊するなど、「政治とカネ」の問題で大揺れとなりました。
当時も企業団体献金は禁止されていたのですが、焦点はだんだんと自民党の長期政権を問題視する点へと移っていったのです。
最終的には、多党乱立の原因とされた中選挙区制の廃止に至ることとなり、以降は定数是正といえば定数の削減が主体になってきました。
今回、議員定数の削減が実現した場合は、さらに定員が減少していきやがては300人台まで減少する可能性もあるでしょう。
そもそも国会議員の適切な人数とはどの程度なのか、他国の状況なども踏まえたうえで考えてみましょう。
日本の国会議員の定数は衆院の465人、参院の248人を合わせても人口比では1対17万人程度です。
英国では5万人未満に1人、フランスはおよそ7万人に1人など、G7の中で比較すると日本は下から2番目という少なさであり、決して多くはありません。
今回議論されている衆院議員定数の削減に関しては、地方の声が届きにくくなることや人口が少ない地域の意見が届かなくなることが懸念されているのです。
予定通り臨時国会で成立させることよりも、まずは政治改革について根本的な議論を重ねる必要があるのではないかとも考えられています。
まとめ
衆院議員定数の削減問題は以前から度々出されているのですが、今回は自民党に協力した日本維新の会からの強い要望もあって成立する見通しです。
問題が浮き出してきたのは、自民党を中心とした裏金問題や政治献金の禁止などから論点をずらすためだという意見もあり、野党からも批判が集まっています。
削減されるのは比例代表が考えられていますが、削減されると少数意見や地方の意見などが伝わりにくくなる可能性もあるでしょう。