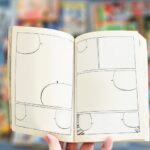現在、日本は自民党と公明党の連立政権となっていますが、人数的には自民党のほうが多いため自民党が主導といえるでしょう。
結成時点から与党であり戦後では最も長く与党となっている政党ですが、そもそも自民党はどのようにして成り立った政党なのでしょうか?
自民党の成り立ちについて、解説します。
自民党の成り立ち
自民党は、正式な名称では自由民主党といい、自由民主主義の理念を掲げ常に改革を進める自由主義の保守政党を標ぼうしている、日本の与党です。
自由民主党が結党されたのは1955年で、当時日本社会党が台頭してきたことを危惧して自由党と日本民主党が合同して結党されました。
板垣退助が創設した政党である自由党が源流であり、戦前の二大政党であった立憲政友会、立憲民政党が起源となっているのです。
他にも、翼賛議員同盟や翼賛政治開、大日本政治会、並びに翼賛体制に批判的な同交会や護身同志会、日本自由党、日本進歩党、日本協同党などの流れも汲んでいます。
自民党の政治は執行部ではなく、所属している政治家の派閥同士の駆け引きによって成り立つというのが常態化していたのです。
なぜかといえば、1994年まで採用されていた中選挙区制によって選挙区ごとに複数候補を立てる必要があったことが原因となっています。
同じ選挙区で出馬する相手は、同じ政党であってもライバルとなるため、党本部の応援を独占することができず個人で講演会の組織や派閥への加入が必要となったのです。
日本では1980年代まで官僚主導と評される、経済体制を自民党が主導していく状態が続いていました。
欧米では金融資本主導の新自由主義といわれる体制だったのですが、日本の体制は国家資本主義に近い、産業資本が中心となった体制になっていたのです。
当時は第一野党の日本社会党が分裂して衰退していったのですが、自民党は護送船団方式で産業政策、農業補助金の交付、地方の公共事業などで政府が介入、調整していました。
55年体制という経済格差を解消するための政策が行われ、自民党の政策は厚い中間層を生み出して日本の文化力、経済力の源泉としたのです。
1980年代後半にはバブルが崩壊したことで、自民党の経済政策も大きな転換を迎えることとなりました。
日本の人口減少対策として、出生率を改善することで自然と増やしていく方針ではなく移民受け入れによる社会増で解決するという立場になり、移民政策を実施したのです。
日本の外国人人口は2013年以降右肩上がりとなり、現在では総人口の3%を外国人が占めるようになりました。
自民党は長い間日本の政治を支配する政党となり、1993年に非自民政権の細川内閣が成立するまで、38年間一貫して政権与党だったのです。
自民党が結党以来野党となったのは、1993年から1994年にかけての非自民・非共産連立政権と、2009年から2012年の民主党政権の期間に限られます。
多数の政治家を輩出している政党でもあり、非自民勢力の大物政治家の中にも自民党出身者が多数いるのです。
歴代内閣総理大臣の中でも、日本新党の細川護熙や新生党の羽田孜、民主党の鳩山由紀夫などはもともと自民党出身で他党になってから内閣総理大臣になりました。
他にも小沢一郎や亀井静香、岡田克也、鈴木宗男、石原慎太郎などもいて、自民党成立後の歴代総理大臣で自民党所属歴がないのは村山富市、菅直人、野田佳彦の3人だけです。
自公連立政権について
自民党は第一与党ではありますが単独政権ではなく、公明党との連立政権という形を長い間続けてきました。
10月10日に公明党が連立政権から離脱することを表明したため、今後は自民党の単独政権となるのですが、なぜ連立政権となったのでしょうか?
そもそも連立政権というのは珍しいものではなく、第2次中曽根内閣では自民党と新自由クラブの保守連立政権、細川内閣や羽田内閣は非自民・非共産連立政権となりました。
村山内閣、第1次橋本内閣も日本社会党や社会民主党、新党さきがけとの連立政権で、小渕第1次改造内閣では自由党との連立政権だったのです。
公明党が加わったのは小渕第2次改造内閣からで自由党との3党連立政権となり、以降は森内閣や第1次小泉内閣で保守党や保守新党とともに連立政権に加わっていました。
第二次小泉内閣からは自民党と公明党の2党だけの連立政権になったのですが、政権交代によって自民党と公明党はどちらも与党から外れることになったのです。
連立政権が成立するのは、多くの場合どの政党も単独で過半数を制することができないという理由があります。
他の政党よりも議席数が多くても、過半数に満たない場合は野党の反対によって政策の決定が妨げられてしまうため、過半数になるよう他の党と協力するのです。
海外でもしばしば連立政権になることがあり、特にドイツは比例代表制を採用していて過半数に満たないことが多いため、戦後の内閣は全て連立政権となっています。
日本は自民党が結党されるまでの間は連立政権が多くみられ、自民党も長い間単独政権だったものの1983年以降はたびたび連立政権となっているのです。
1999年以降は公明党との連立政権を36年にわたって続けてきたのですが、今回公明党が離脱することになったため単独政権にならざるを得なくなりました。
今後、他の政党と組む可能性もあり、公明党と再び連立政権になる可能性もあるのですが、しばらくの間は単独政権を続けることになるでしょう。
公明党とは閣外協力の関係になるといわれているものの、今までより政策に対して反対される可能性は確実に高くなると思われます。
自民党が今後政策を成立させるためには、野党の中で反対意見が少なくなるような内容にする必要があるため、今まで以上に野党への配慮が重要となるでしょう。
まとめ
自民党は正式名称を自由民主党という日本の与党で、多くの政党の流れを汲んで1955年に結党してから70年の間、ほとんどの期間与党として政権を担っていました。
多数の政治家を輩出している政党であり、他の党の大物政治家であっても自民党出身者が多く、所属歴がない内閣総理大臣は3人だけです。
36年間公明党との連立政権を続けてきたものの、公明党が連立政権からの離脱したため今後は単独政党として政権を担うことになります。