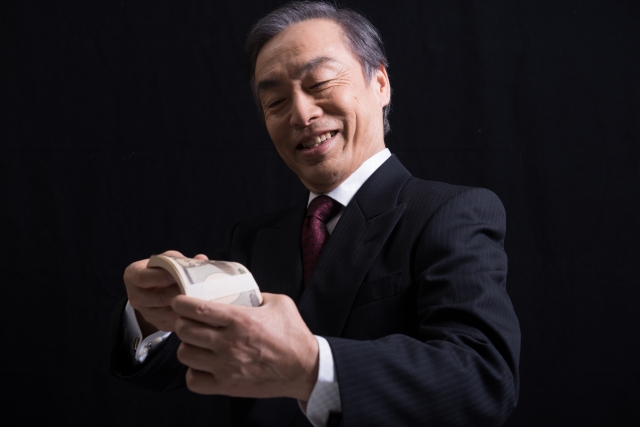政治とカネを巡っては、以前から国民の不信感を掻き立てる原因となっており、国会でもたびたび議論されてきました。
しかし与党である自民党が企業献金に大きく依存してきたため反対しており、禁止は実現されなかったのです。
今、再び起こっている企業・団体献金問題について解説します。
自民党が景気となった企業・団体献金問題
自民党は長い間政治とカネ問題の矢面に立たされ続けており、2022年から2023年にかけては特に、派閥の政治資金パーティーによる巨額の裏金が次々に発覚したのです。
有力議員の多くが裏金議員となり、党の役職を解かれてしまうなど深刻な事態へと陥ることになりました。
自民党が2024年10月の衆院選、翌年7月の参院選と連続して敗北した原因も、裏金問題に対して有権者が厳しい判断を下したからでしょう。
国会でも、政治とカネ問題の根幹となる献金問題についてどう扱うべきか、与野党間で協議を続けてきました。
しかし、通常国会会期末となる2025年6月には衆院の政治改革特別委員会理事懇談会は法案を採決せずに、次の国会で審査を続けるという先送りを選択したのです。
審査を続ける継続審議となった法案は、まず企業・団体献金を存続させることを前提として内容の公開を強化するという自民党が提案した法案があります。
実はもう1つあり、献金をそもそも禁止するという野党5党派が提案した法案で、野党側は禁止法案を採決するよう強く求めたものの自民党が同意しなかったのです。
企業・団体献金問題に関しては、自民が容認し、立憲民主党をはじめとした野党が反対する図式が常態化しています。
企業献金問題については1970年代から顕在化しており、国政選挙では当選するのに5億円使わなくてはならないといわれるほどだったのです。
自民党総裁選にも何十億円ものカネが費やされたといわれていましたが、原資となったのはほとんどが企業献金といわれています。
既に問題が顕在化してから半世紀が経過しているのに、まだ根本的な解決に至っていないというのは有権者もあきれるのが当たり前でしょう。
そもそもなぜ企業・団体献金は問題なのか
政治家が企業・団体献金を受けるのが当たり前になっているのですが、そもそもなぜ問題視されるのかと疑問に思うかもしれません。
たとえ政治資金規正法などの法律で認められているとしても、政治の意思決定を歪める原因となる恐れがあるため、制限を加える必要があるのです。
政治とカネが問題視され始めた1970年代に、日本では大気汚染や水質汚濁などの公害が社会問題となるほど表面化していました。
しかし、政府や与党である自民党は公害企業への対策が遅れており、原因として該当企業から巨額の献金を受け取っていたことが分かったのです。
また、1974年には第一次オイルショックに伴って石油ヤミカルテル事件が起こりましたが、自民党が石油販売会社に献金を増額するよう要求していたと追及されました。
政治献金は癒着につながるというのは何も過去の話ばかりではなく、研究開発費を使った企業への法人税を要求する租税特別措置などにも影響しているのです。
租税特別措置による減税額が大きい業界ほど、自民党への政治献金額が多いと新聞で報じられたこともありました。
自民党が与党に戻ってから、2013年から2019年の間に減税額が大きかったのは自動車などの「輸送用機械器具製造業」であり、総額は1兆4000億円にもなったのです。
次いで多いのが「化学工業」で8700億円、「電気機械器具製造業」の5300億円とつづいたのですが、どの業界も自民党への献金と便益との相関関係がみられました。
法学研究者や法曹関係者は、政党に何も要求しないのに巨額の献金をする企業が存在するはずがない、と批判を重ねていたのです。
しかし、企業による政治献金は違法というわけではなく、かつての八幡製鉄事件では最高裁において、1970年に企業献金は合法という判断が下されました。
自民党も最高裁の判決を根拠として、企業・団体献金は合法であり合憲であるという立場を取っているのです。
毎年約24億円を自民党側に献金している日本経済団体連合会の十倉雅和会長も、民主主義を維持するコストを企業が負担するのは社会貢献だと述べています。
しかし、政治とカネをめぐる根本の問題が政治献金にあることは明らかなので、政治献金の禁止をめぐる議論は今まで途切れることなく続いてきたのです。
現在につながる企業・団体献金の禁止は、1994年に成立した一連の政治改革4法に盛り込まれたものを根拠としています。
当時の政治改革の1つとして政治資金に関する改革も行われ、企業団体献金の廃止と代わりの資金源として税金を原資とする政党交付金を導入することでした。
ただし、急に企業献金を禁止すると政党運営などに大きな支障が出ることを懸念し、5年後をめどに献金のあり方を見直すことを政治改革4法の附則で明記しました。
当時、非自民連立政権の細川護熙首相と野党だった自民党の河野洋平総裁は、政治改革に合意した際に5年後の廃止をはっきり表明したと強調したのです。
ところが、結局は合意について無視され続けており、河野氏は合意から25年が経過した時点での回顧録で自民党と国会の姿勢に強い疑問を呈しています。
以降も企業・団体献金の禁止を求める野党側と、全面禁止には強硬に反対し部分改革で対応しようとする自民党の間で、駆け引きは続いてきたのです。
高市政権誕生の際、自民党と維新が交わした合意書では、企業・団体献金について現時点で最終結論を得るまでには至っていないと指摘しています。
ただし、多額の献金が政策の意思決定を歪めるという懸念を払拭し、国民に信頼される政治資金の在り方を追求する制度改革が必要という課題意識は共有するようです。
献金については、両党による協議体を2025年の臨時国会中に設置し、高市氏の任期中に結論を得ることを表明しています。
しかし、合意に際して維新は突然、献金問題よりも衆院議員の定数是正を優先するという主張を出して、献金問題を後回しにする姿勢を見せたのです。
現在開会中の臨時国会で、自民と維新は国民を納得させる成案を得ることができるのかに注目されます。
まとめ
自民党は長い間企業・団体献金問題が顕在化しており、2022年、2023年には政治資金パーティーを通じて巨額の裏金を作ったことも明らかになったのです。
以前から問題視されており国会でも何回も野党から追及を受けているのに十分な規制もされなかった献金の問題ですが、そもそも合法であることがおかしいのかもしれません。
日本維新の会も、献金問題より衆院議員定数の削減を優先するスタンスに変えているあたり、根深い問題でしょう。