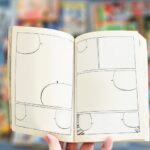近年、職場での人間関係で特に注意しなくてはならないものが、多くの種類があるハラスメントです。
かつてはセクハラ、パワハラなどがほとんどでしたが、最近では多岐にわたるハラスメントがあるため把握するのも難しいでしょう。
ハラスメントの種類には何があるのか、解説します。
ハラスメントの種類について
ハラスメントというのは嫌がらせや迷惑行為といった意味で使われている言葉で、相手の嫌がること、不快感を与える行動などが当てはまるのです。
ハラスメントというのは一つの基準で定められているものではなく、法令に定義されているものと定義はないものの社会通念上ハラスメントとなるものがあります。
代表的なものにはセクシャルハラスメント(セクハラ)があり、性的な言動により不利益を与えるハラスメントです。
例えば、相手に許可なく触れたり身体的な特徴について言及したり、性的な言動をしたりした場合が当てはまります。
セクハラのうち対価型セクハラといわれるものは、性的な言動をする代わりに優遇を約束し、拒否すると不利益を与えるものです。
環境型セクハラといわれるものは、職場内で性的な言動をすることで労働者の就業環境に悪影響があるセクハラをいいます。
同じく定義されているパワーハラスメント(パワハラ)は、職場で上司から部下に対する言動や集団から個人に対する言動などと定められているのです。
通常の業務を支持するだけなら問題ありませんが、業務を逸脱した言動や労働者の就業環境を害するような言動などが当てはまります。
パワハラには、身体的な攻撃、精神的な攻撃、人間関係からの切り離し、過大な要求、過小な要求、個の侵害という6類型が定められているのです。
マタニティハラスメント(マタハラ)という、妊娠や出産、育児に関する言動で女性労働者の就業環境を害するハラスメントもあります。
類似するもので、パタニティハラスメントという男性労働者に対して育児に関する言動で就業環境を害するハラスメントもあるのです。
また、両親の介護などで介護休業を利用する労働者の就業環境を害する言動もハラスメントに当てはまり、ケアハラスメントと呼ばれます。
法令では定義されていなくてもハラスメントとなることもあり、精神的な嫌がらせなどはモラルハラスメント(モラハラ)といわれるのです。
職場において立場を利用した精神的な嫌がらせはパワハラですが、モラハラは対等な関係で精神的に優位な相手からの嫌がらせなどが当てはまります。
性別によって社会的役割を差別して嫌がらせをするとジェンダーハラスメントとなり、性的な言動に限らず男性だから、女性だからという固定観念に基づいた言動のことです。
お茶くみは女性の仕事、営業は男性の仕事というのはジェンダーハラスメントの典型的な例ですが、合理的な判断から男女で扱いが異なる場合は異なります。
お酒に関する迷惑行為はアルコールハラスメント(アルハラ)といい、飲み会への参加の強要や不参加による嫌がらせなどはアルハラです。
リストラハラスメントという、リストラしたい相手に対して嫌がらせを行い、自主退職するように仕向けるというハラスメントもあります。
通常は人事権を有している役員や管理職が主導して行うことが多いため、同時にパワハラに当たることもあるのです。
近年は職場にパソコンをはじめとしたIT機器が増えているため、ITに関して詳しくない労働者に対するテクノロジーハラスメントもあります。
機器の使用方法を教えるのではなく、使えないことを過剰な言葉で責めたり、使いこなせなければできないような業務を課したりすることなどがテクハラです。
ハラスメントの段階と影響
ハラスメントは、企業の社内規定に違反する行為などが最も軽度で、違反した従業員に対しては規定に従った処分が下されます。
パワハラやセクハラ、マタハラ(パタハラ)、ケアハラは労働法上で規制されているハラスメントです。
労働法では、企業に対してハラスメントを防止して対応するための必要な措置を講じるように義務付けられています。
ハラスメントの防止や対応に関する措置を講じる義務を怠っていると、厚生労働大臣による行政処分の対象になる可能性があるのです。
ハラスメントが原因で被害者が権利を侵害されてしまい損害を受けると民法上の不法行為になり、被害者は加害者に対して損害賠償請求を行うことができます。
例えば、上司が部下を殴って病院で治療を受けたり、会社を休んだりすることになった場合は、治療費や休業による金銭的損害を上司が賠償しなくてはいけません。
最も悪質なものは刑法上の犯罪に当てはまり、他人に対して暴力をふるうことは暴行罪、ケガをさえたら傷害罪、不特定多数を対象に他人の名誉を棄損すると名誉棄損罪です。
他人を公然と侮辱した場合は侮辱罪、暴行や脅迫を用いて被害者が反抗できないようにしてわいせつな行為を行うと、強制わいせつ罪になります。
社内でハラスメントが横行していると、企業は従業員の離職率が高まって優秀な人材が流出してしまい、会社の評判も下がって人材確保も困難になるでしょう。
また、法的には安全配慮義務違反や被害者からの損害賠償請求、厚生労働大臣による行政処分を受けてしまうこともあります。
被害者は今まで通りに働ける環境が損なわれてしまい、メンタルヘルスが悪化して精神疾患を発症することもあるでしょう。
加害者は自身の評判を落として社会的地位を失ってしまうことにもつながり、社内規定に違反して懲戒処分を受ける可能性もあります。
また、法的に被害者からの損害賠償請求を受ける可能性もあり、刑法上の犯罪に該当して罪を問われることもあるのです。
まとめ
現在はハラスメントの種類がかなり増えているため、どのような行為が当てはまるのかはっきりとしないかもしれません。
法令に定義されているハラスメントには性的なものや立場を利用したもの、介護休暇に関するものや妊娠などに関するものがあり、他にはお酒に関するハラスメントもあるのです。
内容によって段階別に分けられ、企業内での規定違反や行政法上の行為、民法違反による罰則、刑法による犯罪となる行為などもあります。